顔色を伺い、言わなきゃいけないことから目を背けて結果的に良くない方向に進んでしまうことを防ぐ環境作りの事だよ。
心理的安全性は職場で必須スキルだということがGoogleの研究【アリストテレス】にて認知されました。事実仕事でやめる人のほとんどが人間関係であり、転職サイトでも人間関係を意識した掲載の仕方にも注力しています。
この世界では人間関係の悩みしか存在しないと言った心理学者のアドラーが残した通り、私たちはこの「話し合える」環境を作り出すことがもっとも役割を与え、チーム全体を良くしていけるのだと確信しています。
はじめまして
私は心理的安全性を習慣化するために日夜研究をしている〝おのざる〟と申します。本業は看取り介護施設で働く介護長です。
そんな介護施設は人対人の中でも最上級に人間関係についての悩みが尽きない環境です。お互いに顔色を伺いながら仕事をしつつ、おじいさん、おばあさんの暮らしを支えていくのでストレスは驚くほどにかかってしまいます。
当然のことながら喧嘩は絶えず、パワハラ、モラハラなんてものは当たり前、過呼吸や鬱発症などありとあらゆる人間関係での地獄を経験してきました。
「でも本当はいい人なんだけどね」「悪い人ではないんだけどね」つい強く言ってしまうパワハラ気質な人に対して浴びせ合うこの言葉が私は大嫌いです。
「悪い人じゃないことなんてわかってる」しかしそのうえで発言ができなくなり、お互いの不満がたまって本来言いたくもないことを言ってるのかもしれません。それでもその人自身を理解してみる行動を取れるのであれば言い方も変えられます。
いじめた側は先生に「ちょっと遊んだだけですよ」と言って『まぁこの子は普段から優しいからな』と目をつむっているようなそんな感覚になるんです。やられた人しかわからないこの苦しみをどうにか言語化して確固たる武器にしたい。
そう思ったからこそ本を読み進め、私の最も得意とする人間関係にフォーカスをあてながら知識を蓄えてきました。
そこで出会ったのが心理的安全性です。パワハラなどで無理やり強くした組織がなぜニュースになってしまうのか。安全に見えるような環境でもなぜ退職者が続出してしまうのか。
心理的安全性を理解するためにもまずはこちらの【✅なぜ「あの人」は意見を言ってくれないのか~世界一やさしい心理的安全性の活かし方~】をご覧ください。↓
あわせて読みたい
①なぜ「あの人」は意見を言ってくれないのか~世界一やさしい心理的安全性の活かし方~
・心理的安全性とは ひとことで言えば「顔色」を気にしないで意見を伝える環境 賛成も反対も意見をはっきりと伝えることが心理的安全性がある環境と言えます。 しかし「...
心理的安全性について少し理解できましたでしょうか?
最終的に行きつく先はさきほどのブログ内でもあった、夫婦、親子の家庭環境に依存するものだと結論付けました。当然将来にかかわる友人、先生、先輩、上司で180度変わっていくことは間違いありませんが、大前提親子関係=家庭環境=でもその前に夫婦関係など家庭でおこるすべての事に目を向けなければいけないと思っている方にこの習慣化メゾットは存在します。
ここからはさらに詳細に内容を書いたものをそれぞれ配置しています。読者様には今の状況で気になったものを読んでいただけたら幸いです。
心理的安全性とは、何らかの恥ずかしい思い、疎外感、罰などを恐れることなく、❶仲間として認められ、❷安全に学べ、❸安全に貢献し、❹現状打破に安全に挑戦できる、と感じられる状態を指します。
排除→インクルージョン(多様を受け入れ活かしあうチーム)→学習→貢献→挑戦
✅【聞く】・【排除、操作、ぞんざい】・【自分から心を開く】=受け入れ
✅【化石の悪習慣】、【管理下に置かれすぎていないか?】
(仮)夫婦編まとめ➤【5記事】➤それぞれSAの習慣
✅「ありがとう返し」が作りだす感謝の循環【気持ち】
あわせて読みたい
②夫婦仲が悪いと子供の成長を妨げるのかな?~心理的安全性は「○○の気持ち」で作り出せる~
旦那が仕事を理由に家庭のことを一切しない。働いてくれているから何も言えないけど、家のことを少しはしてほしい。(ちょっとくらい私のこともいたわってくれても・・...
✅信頼貯金なんて存在しなかった【勘違いの克服】
あわせて読みたい
③育児必見!夫婦の信頼貯金なんて存在しなかった。夫婦仲のよさが子供に影響する!?
夫に余計なことを言われてイライラしている・・・ ぼくもついつい余計なことをいっちゃうな ひとことって本当に恐ろしい力をもっていると思わない? 信頼が壊れるような...
✅自信がなかった夫が妻のおかげで取り戻せた【自信】
あわせて読みたい
④会社で否定され続けて自信をなくした僕が妻のおかげで取り戻せた~アイデアは形になる瞬間~
3年前自信喪失して会社をやめたんだ 会社なんて自信なくすことばかりだよね 介護長として働いていたんだけど・・・板挟みにあって・・・会社にいるのが辛かったんだ。...
✅副業・SNS夫婦の価値観で時間を作り出すことが困難【さらなる挑戦】
あわせて読みたい
⑤副業・SNSを頑張りたいんだけどパートナーから否定された。僕が作り出せたコツと妻の理解まで時間がか...
副業時代だからやりたいんだけど家族の時間がないってことで妻が認めてくれないんだよなぁ 僕も認められるとかなかったな え?じゃあどうしたの? 会話を増やしていった...
(仮)親子編まとめ➤【6記事】➤それぞれSAの習慣
✅子どもを決めつけてしまう9つのワケ!
あわせて読みたい
⑥子どもを決めつけてしまう理由9選。嫌われる勇気からも学んでおこう【決めつけない】
子どもについつい怒鳴ったりしてしまう。結局寝顔を見て反省する毎日・・・ わかるよ・・・勝手に決めつけて期待してしまうんだよね そっか確かに期待もしてしまってる...
✅子どもが映像を見たあとに興奮してしまう問題。「それ心理的安全性が解決するよ」【視点替え】
あわせて読みたい
⑦寝る前の子どもが興奮しちゃう理由は映像が問題!脱スマホ!その方法は一つしかない!
ウチの子夜寝るまでに2時間以上かかっちゃう… 結構かかってるね。興奮しちゃうのかな? 確かに寝るまでテレビやスマホを見てるかも・・・ きっとそれが原因だね・・・ ...
✅エモトークが幼児の心を動かすきっかけになる【子供の感情と向き合う】
あわせて読みたい
⑧子育てのイヤイヤ期を解消!エモーショナルインテリジェンスが幼児の心を動かすきっかけになる【子供の...
子どものイヤイヤモードどうにかならないのかな? ウチもイヤイヤ期は奇声などみられたなぁ 子どものイヤイヤ期って何をしても泣き叫んでいるイメージがありませんか?...
・親に読んでほしかった本を読んでわかったことベスト9【勝ち負けじゃない】
あわせて読みたい
⑨親に読んでほしかった本を読んでわかったことベスト9【勝ち負けじゃない】
「親にもっとこうしてほしかった」と思うことが、大人になってから増えた気がします。でも、それをただ嘆いていても仕方がありません。むしろ、自分がその"親になりたか...
・子どもがしていることはほとんどすべて親の影響【親の姿勢が9割】
あわせて読みたい
⑩子どもがしていることはほとんどすべて親の影響【親の姿勢が9割】
「どうしてうちの子はこんな行動をするんだろう?」と悩んだことはありませんか?子どもが泣き叫んだり、物を壊したり、友達と喧嘩したり、親として理解に苦しむ瞬間が...
・おさるのジョージから学ぶ子どもへの声掛け~心理的安全性のすべて
あわせて読みたい
⑪おさるのジョージから学ぶ子どもへの声掛け~心理的安全性のすべて
「おさるのジョージ」に登場する黄色い帽子のおじさんを覚えていますか?子どもから大人まで愛されるこのキャラクターは、ジョージに対して一度も怒ることがないことで...
(仮)性格編まとめ➤【5記事】➤それぞれ
・ビッグファイブ理論と心理的安全性【性格がチームを変える】
あわせて読みたい
⑫ビッグファイブ理論と心理的安全性【性格がチームを変える】
「チームの雰囲気がギクシャクしている」「もっと意見を言い合える環境にしたい」と感じたことはありませんか?職場やプロジェクトの成功には、チームの心理的安全性が...
・自分のミスを伝えミスを共有しミスを楽しむ関係【オープンにする】
あわせて読みたい
⑬自分のミスを伝えミスを共有しミスを楽しむ関係【オープンにする】
「ミスは隠すもの」「ミスは恥ずかしい」という考え方に縛られていませんか?職場や家庭、どんな場面でもミスは避けられません。しかし、そのミスを隠すのではなく、オ...
・本などの文字を読む行為だけではダメ!〝おはなし〟という対話が表現力・理解力に大きな影響がある【会話が聞く力を育む】
あわせて読みたい
⑭本などの文字を読む行為だけではダメ!〝おはなし〟という対話が表現力・理解力に大きな影響がある【会...
「本を読むことが子どもにとって大切」とよく言われます。確かに、本を通じて子どもは多くの知識や言葉に触れることができます。しかし、それだけでは十分ではありませ...
・できないことよりもできることに目を向ける【大人に対しても】
あわせて読みたい
⑮できないことよりもできることに目を向ける【大人に対しても】
大人になっても「自分にはこれができない」「あの人と比べて自分は劣っている」と、できないことばかりに目を向けてしまう瞬間はありませんか?このような考え方は、心...
・これは許せない。自分の気持ちと行動が招く失敗【調整力と柔軟な心がチームをよくする】
あわせて読みたい
⑯これは許せない。自分の気持ちと行動が招く失敗【調整力と柔軟な心がチームをよくする】
「どうしてこんなことをされたのか理解できない」「これだけは絶対に許せない」。日常生活や職場で、こんな感情を抱いたことがある人は多いのではないでしょうか。しか...
(仮)おもいやり~心~編まとめ➤【5記事】➤それぞれ
・自分の心のスペースを知ることで相手を思いやれる
あわせて読みたい
⑰自分の心のスペースを知ることで相手を思いやれる
人間関係において、相手の気持ちを理解したり、思いやりを持った行動を取ることは重要ですが、そのためにはまず自分の心のスペースを知ることが欠かせません。忙しい日...
・アサーティブという難しそうな言葉はただの思いやり
あわせて読みたい
⑱アサーティブという難しそうな言葉はただの思いやり
「アサーティブ」という言葉を耳にしたことがありますか?一見すると難しく聞こえるこの言葉は、実はとてもシンプルな概念です。アサーティブとは、自分の意見や気持ち...
・思いを与えることができれば人間関係うまくいく
あわせて読みたい
⑲思いを与えることができれば人間関係うまくいく
「どうすれば人間関係がもっとスムーズになるのか?」そんな問いを抱えたことはありませんか?その答えの一つが、思いを与えることです。思いとは、相手に対する関心、...
・まるで家族のように思いやりを持つことができるコツ【潜在意識】
あわせて読みたい
⑳まるで家族のように思いやりを持つことができるコツ【潜在意識】
「どうすればもっと人間関係が円滑になるのか?」そんな問いを抱えている方にお伝えしたいのが、「まるで家族のように思いやりを持つ」という考え方です。これは単に他...
・おもいやりが人を失敗に追い込むのか?言葉の選択が求めるもの
あわせて読みたい
㉑おもいやりが人を失敗に追い込むのか?言葉の選択が求めるもの
「おもいやり」は人間関係を良くするために欠かせない美徳とされています。しかし、その思いやりが、時に人を失敗に追い込む可能性があるとしたらどうでしょうか?言葉...
(仮)職場の人間関係編まとめ➤【5記事】それぞれ
・看護師たちから盗み聞きした好きになっちゃう男の条件No1とは?
あわせて読みたい
㉒看護師たちから盗み聞きした好きになっちゃう男の条件No1とは?
「好きになっちゃう男って、どんな人だと思う?」介護の現場で働いていると、ふと耳に入ってくる看護師たちの会話が意外と面白かったりします。先日、私が仕事をしてい...
・仕事はできるけどコミュ障VS仕事はできないけど社交的
あわせて読みたい
㉓仕事はできるけどコミュ障VS仕事はできないけど社交的
職場で「仕事はできるけどコミュニケーションが苦手な人」と「仕事は不得意だけど社交性が高い人」、どちらがよりチームにとって重要なのでしょうか?この2つのタイプは...
・ウソをついて逃げてしまう状態をどうしたらいいのか?正直者はバカをみない
あわせて読みたい
㉔ウソをついて逃げてしまう状態をどうしたらいいのか?正直者はバカをみない
「ウソをつくことでその場を切り抜けたけれど、後で罪悪感や後悔に苛まれる」。こんな経験をしたことはありませんか?人は、失敗を恐れるあまりウソをついてしまうこと...
・報連相が大切っていうけど心の声を聴けない理由は何だと思いますか?ヒントは雑相
あわせて読みたい
㉕報連相が大切っていうけど心の声を聴けない理由は何だと思いますか?ヒントは雑相
職場や家庭で「報連相(報告・連絡・相談)」が大切だと言われることはよくあります。しかし、形式的な報連相に終始し、本当に必要な「心の声」を聴けていない状況が多...
・主体的に意見がでるチームと言われたことだけやろうとするチーム
いかがでしょうか?
ここまで読んでいただいたものは本を購入したものよりも価値のあるものになるかと思われます。しかしそれでも家庭環境によって大きく違いが存在します。
私の場合は・・・と気になった方に習慣化メゾットの資料をプレゼントします。
さらにもっと知りたい方に習慣化メゾットプログラム
・心理的安全性は習慣で作れる
【日本心理的安全性アドバイザー認定資格】の受講をお勧めします。
あわせて読みたい
日本心理的安全性アドバイザー協会(JASA)認定資格
心理的安全性とは 心理的安全性とは、簡単に言うと「安心して自分の意見を言える環境」のことです。これは学校や家族、友達との関係でもとても大切です。心理的安全性が...
こちらは自分の家庭環境を整えつつ、人に教えていくことができる資格となります。
「完全受講型資格授与」になりますので履歴書にも書くことができます。
日々辛い、苦しいは嫌なことがおこったときだけではありません。言いたいことが言えなかったときや、話し合えない環境に身を置いていることで「孤独感」を味わいダンダンと心が遠ざかっていきます。
育児に忙殺されれば忘れることができるかもしれませんが、兼山の上を歩くがごとし大変な道のりです。一人で悩まずに一緒に進むことができることが心理的安全性を文化にするための道のりの一つだと思っています。
一緒に文化にしていきましょう。
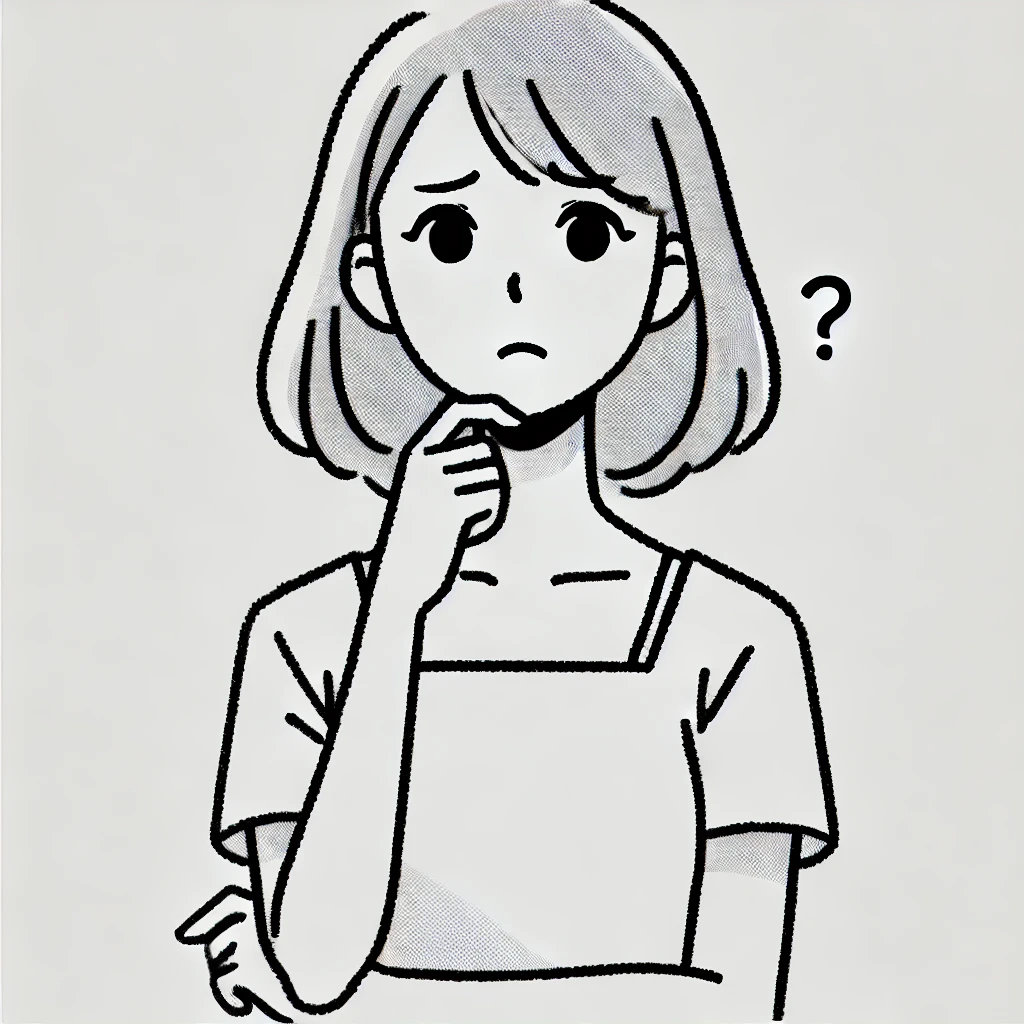





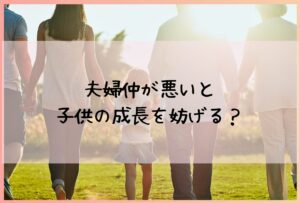
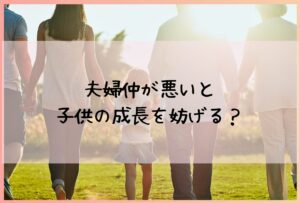
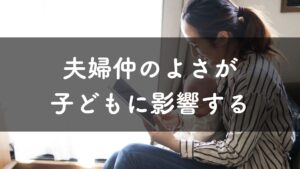
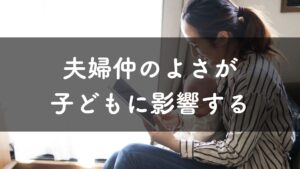
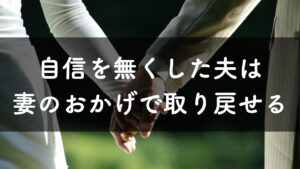
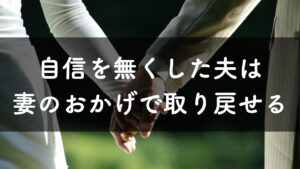
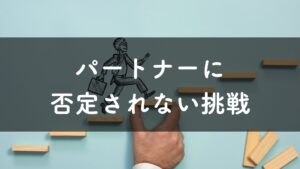
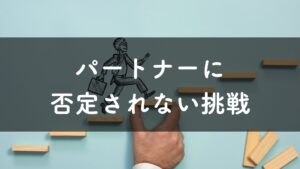
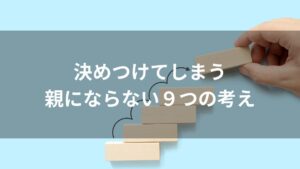
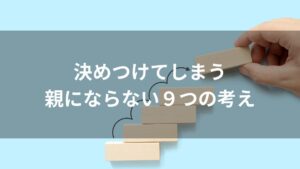
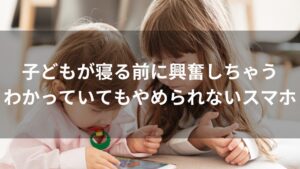
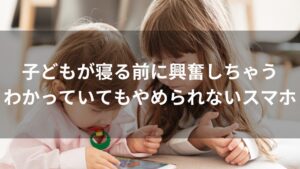






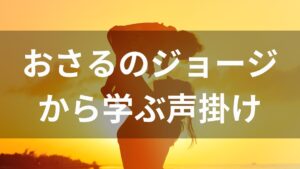
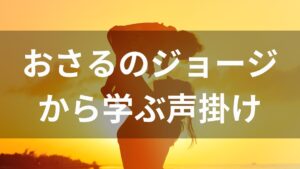






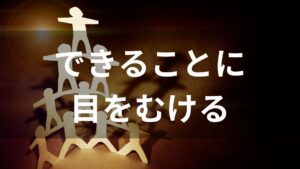
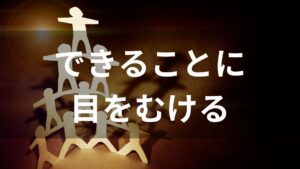
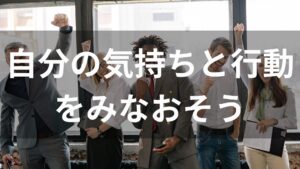
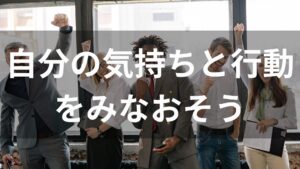
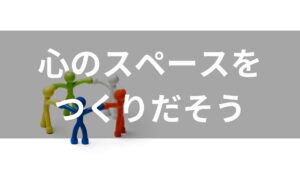
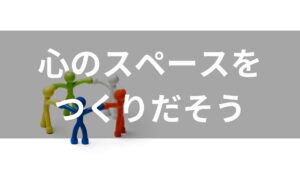




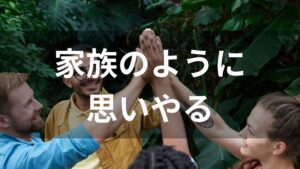
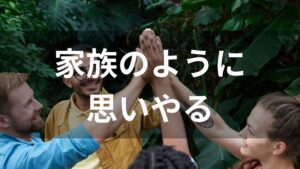
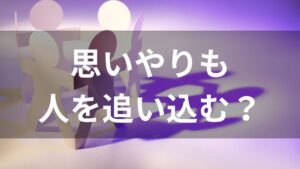
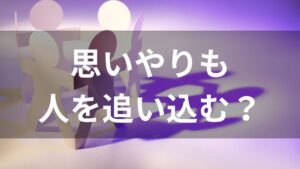




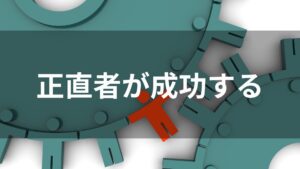
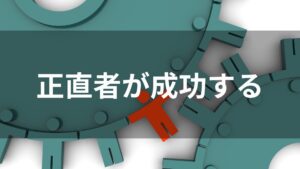





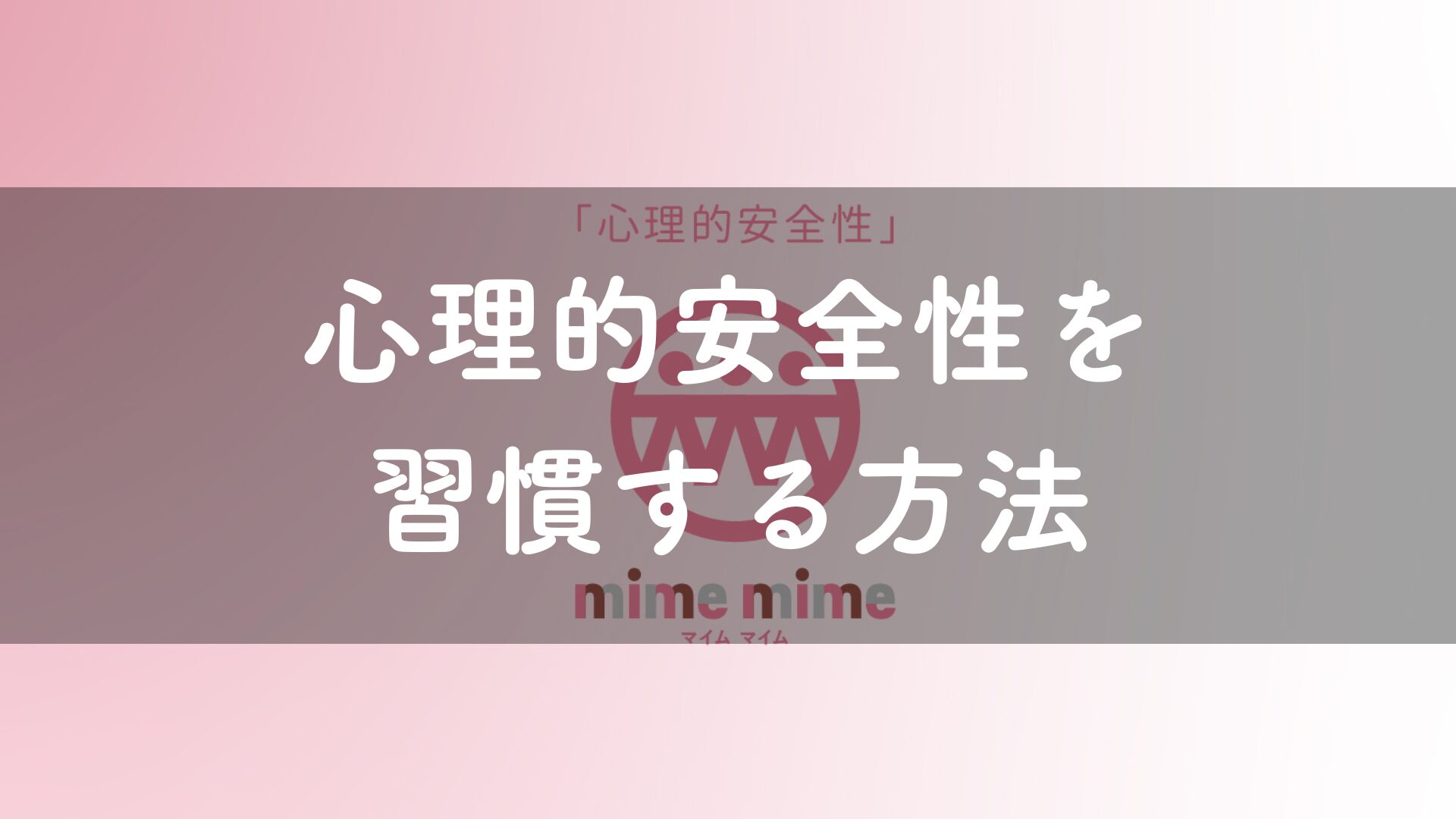
コメント