「どうしてこんなことをされたのか理解できない」「これだけは絶対に許せない」。日常生活や職場で、こんな感情を抱いたことがある人は多いのではないでしょうか。しかし、この感情をそのままにしておくと、チームや人間関係を壊してしまう可能性があります。
この記事では、心理的安全性の観点から「許せない」という感情にどう向き合うべきか、また、それが引き起こす失敗をどう活用できるかを深掘りします。さらに、調整力と柔軟な心を持つことで、どのようにチームや関係性を改善できるのか、具体的なアプローチを交えて解説します。
感情が引き起こす失敗
「許せない」という感情は、衝突やミスを引き起こす大きな要因です。この感情に飲み込まれると、次のような問題が発生します。
- 対立の激化
- 小さな誤解やミスが大きな問題に発展する。
- コミュニケーションの断絶
- 感情的な対応が相手との信頼関係を壊す。
- 心理的安全性の低下
- チーム内で「自分の意見を言えない」という雰囲気が生まれる。
例えば、私の職場で、ある同僚がプレゼン資料を期日通りに用意できなかったことがありました。そのとき私は「こんな基本的なことも守れないなんて」と腹を立て、冷たく接してしまいました。しかし、その後、彼が家庭の事情で大変な時期を過ごしていたことを知り、自分の態度を後悔しました。
調整力と柔軟な心が必要な理由
調整力と柔軟な心は、感情に左右されずに問題を解決するための鍵です。この2つの要素があることで、次のような効果が期待できます。
- 対話の促進
- 問題の本質に迫るための冷静なコミュニケーションが可能になる。
- 解決策の創出
- 一方的な非難ではなく、建設的な解決策を見つけやすくなる。
- 心理的安全性の維持
- チームメンバーが自由に意見を言える環境を作り出す。
例えば、あるプロジェクトで進行が遅れた際、私は感情的になるのではなく、遅れの原因を冷静に分析しました。結果として、タスクの分担が不公平だったことが判明し、再配分することでプロジェクトがスムーズに進むようになりました。
実践的なアプローチ
調整力と柔軟な心を養うための具体的な方法を以下に紹介します。
- 感情を冷静に振り返る
- 感情が高ぶったときは、少し時間を置いて自分の感情を整理します。例えば、「なぜ自分はこんなに腹を立てているのか」をノートに書き出してみると、冷静に状況を分析できるようになります。
- 相手の立場を考える
- 「相手はなぜこの行動を取ったのか?」と問いかけることで、相手の背景や事情を理解する努力をします。
- 建設的な質問を投げかける
- 感情的な非難ではなく、「この問題をどう解決すればいいと思いますか?」と相手に問いかけることで、協力的な対話が生まれます。
私の体験談
ある日、家庭で子どもが大事な書類を汚してしまったとき、私は感情的になって怒りそうになりました。しかし、「どうしてこんなことをしたの?」ではなく、「何をしていたときに汚れてしまったの?」と冷静に尋ねることで、子どもは自分の行動を振り返り、素直に謝りました。その結果、ただ叱るだけではなく、どうすれば同じことが起きないかを一緒に考えることができました。
この経験を通じて、柔軟な心を持つことで、問題を解決するだけでなく、子どもとの信頼関係を深めることができると実感しました。
まとめ
「許せない」という感情は、誰もが持つ自然なものです。しかし、その感情に振り回されるのではなく、調整力と柔軟な心を持つことで、問題を建設的に解決できるようになります。
心理的安全性を高めるためには、まず自分自身の感情と行動を見直し、相手と対話する姿勢を持つことが大切です。この記事で紹介した方法を、ぜひ職場や家庭で実践してみてください。きっと、新しい気づきと成長が得られるはずです。



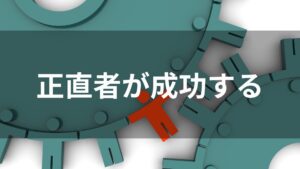


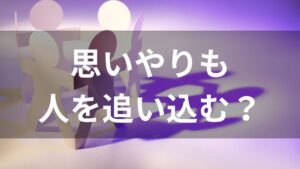
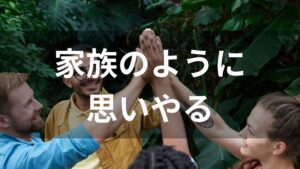


コメント