
ウチの子夜寝るまでに2時間以上かかっちゃう…



結構かかってるね。興奮しちゃうのかな?



確かに寝るまでテレビやスマホを見てるかも・・・



きっとそれが原因だね・・・



でも親1人では難しいんだよなぁ
どうしたらいいのかな?
こんなことってないですか?親としても忙しい毎日なのに子どもを構いながら家事をするのも厳しいです。もし2人、3人と子供がいたらなおさら厳しいです。
さらに仕事で忙しくてワンオペになってしまい親としての切り札でもある動画に身を乗り出すしかなくなっていきます。
Youtubeでは数々のおもちゃ動画があり、1才ではCMのスキップを覚えちゃう子も多いです。操作も容易に覚えて「こんなに静かになるならずっとみてて~(悪いとわかってるんだけど・・・)」と陥ります。
これは一種のドーピングです。ドーピングは使った分だけ効果がありますが、使い続けなきゃいけなくなってしまうという大きなデメリットがあります。
でもこの時間は使いたいという時間ってありますよね。ウチも見せる時間があります。ただし時間を決めて寝る前は液晶を見せないという工夫をしています。
家事や仕事が・・・という声が多くなると思いますが、子どもが寝たあとか朝という選択もあります。その時に無理やり押し込む理由がありますか?
子どもが騒ぎ立てるからどうにもできない。そんな悩みをもっている方は是非ウチ(妻)が実践している方法を5つを紹介します。
1、寝る前の2時間前にはごはんやおやつは食べない
まず寝る前に食事をしてしまうとどんなリスクがあるのでしょうか?ネットで調べてみました。
- 消化活動によって睡眠が妨げられる
- 翌朝に食欲が湧かず、朝食が食べられないといった生活リズムの乱れにつながる
- 胃の活動が続くので眠りが浅くなる
- 代謝が低下してダイエットの妨げとなる
- 胃に負担がかかって食生活が乱れる
今回の記事に関係があるのは一番目の消化活動によって睡眠が妨げられる。ではないでしょうか?
血糖値の変動からアドレナリンがでてしまって興奮して眠れないという結果になっています。
第一に食事を変えなくてはいけません。しかし親が働いており夜ご飯が19時や20時になってしまう場合は要注意です。確かに家族でごはんをすることは大切ですが、早寝早起きして朝に皆そろって食べれた方が会話もはずみます。
可能な限り早い時間にはごはんを子どもだけでも済ませておきたいですね。
ウチでは18時前後には食べ終わっており、たまにアイスも食べますが、遅くても19時までです。21時前後に寝るので3時間開けた方が良いとありますが、2時間でも充分寝るという実感でした。
2、寝る前の3時間前には電気を薄暗くする


紫綬褒章を受章している睡眠の第一人者でもある柳沢正史さん/筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 機構長/教授は現代の電気は明るすぎる。
液晶などみていなくても日照と同じレベルの明るさが睡眠の質を妨げると言われています。
その報告を見たときすぐ妻と19時すぎたら電気を一つにして暗めの設定にしようと決めました。
最初は半信半疑でしたが、電気を暗くしないのとするのとでは大きな違いがありました。子どもの睡眠の質は正直わかりませんが、寝入るスピードは断然薄暗くした方が早いと思います。
それも運よく薄暗くできる機能のついた電気を買っていたのでラッキーでした。薄暗くすると白い光は凍てつくような冷たさを感じて疲れますが、暖色機能もあったのでこちらにして正解でした。
正直これからのパパ1年生になる過去の僕には電気を伝えますね。


実際に使っているものですが、明るさを調整でき、なおかつ2000円台で購入できるのでコスパと子育て睡眠パフォーマンスは最高です。Coizabera LEDシーリングライト
3、映像は19:30まで(寝る1時間半前)に終わらせる
子どもの前でスマホをいじらないようにすることは非常に困難です。どちらにせよ子どもだって触りたがります。僕も少し魔が差して子どもが喜びそうなアプリをダウンロードしてやらせたりしました。
しかし驚くことに19時半を超えてやり続けたときに取り上げると必ずといっていいほど泣きじゃくります(´;ω;`)ウッ…←どころじゃありません。大泣きで暴れます。
この姿をみて思ったのが子供の脳は処理をしきれないのだと思いました。液晶に集中することで脳の処理が行いきれずパンクしてしまう。しかしやりたいというドーパミンがあふれ出てしまっているのでキレて当然です。
それならやってもいいんだけど19時半までにしています。必ずやらせるわけでもなく、ちょっとやってもいいかな、とかやってみたいことがあるんだけど、みたいな感じで一緒に少しやる時間ができたりしました。
夕食が18時前後でお風呂が大体夕食後なのでスマホを触れるのも19:00~19:30までと必然的に限られていきます。
終わりの時間が決まっているから少しやってみよう。とできます。
ここで注意したいことは終わりの時間が決まっていると理解しているのは親だけです。子どもは終わりといわれると反発したくなります。私たちは必ず「もうすぐ19時半になりそうだね。あと何回やったら終わりにするの?」「自分でやめる?パパがやめる?」「どうやって消すんだっけ」と自立的に辞められる工夫の声掛けを行っています。
それは子どもにとって自分で選択したできごとであり、親と一緒に楽しむためのものだと子供が認識している証拠なのだと感じました。
4、寝る前の30分は絵本かおもちゃで一緒に遊ぶ時間を選ばせる
20:30頃~21:00頃には布団に入り最後の一緒の時間です。ここでも子どもに選ばせる時間を作ります。あれもこれもでは子どもも選びきれず「これとこれ」とずっと選び続けます。
しかし最初から1つどちらかと決まっていればぐずることもなくスムーズに選ぶことができます。「今日はお絵本がいい」「パパとレゴしてから寝るの」など選択がすべて子どもの行動に繋がっています。
5、横になったら消灯か常夜灯にしてお話しをする
ここまで順番に寝る準備運動ができました。子どもも選んで満足気だと思います。最後によーいドンをしなきゃいけません。
昔から絵本を読んで子どもが寝ていく。そんなドラマや映画をみたことがあると思います。これも良いのですが、もっともウチや親戚を寝かしつけるときに効果大なのは
「今日はどんなことがあったの?」「こんなことがあってね。こうだったんだよ」と1日のお話しをします。これ一見寝ないでしょ!と思われがちなのですが、子どもは親の声を聴いて安心するのかいつの間にか寝ています。
最近は絵本の大きなカブという本のセリフを記憶してお話ししていくことで自然と寝ています。
どんな感じかというと「大きなカブがありました。おじいさんは子くんを呼んで一緒に引っ張ります。うんとこしょどっこいしょ。それでもまだまだカブは抜けません。さらに次男くんやパパやママ、おばあちゃんの○○と登場人物1人(実際にいる人)登場させて寝るまでカブを抜かせず登場人物を増やし続けます。
これはコトバのシャワーを浴びせている状態になります。
絵本も文字を読んでいるから、音を聞いているから寝ているのではありません。親という安心する存在の声を聴くことで副交感神経が刺激されて睡眠に繋がっていくのです。
3才の息子に対してのお話しが大きなカブですが、0才の赤ちゃんや1才の幼児でコトバがまだわからない子にも効果はてきめんです。なんでもいいんです。1日の出来事などとにかく親が自然と話し続けることを目的にしていくことが大切なのです。

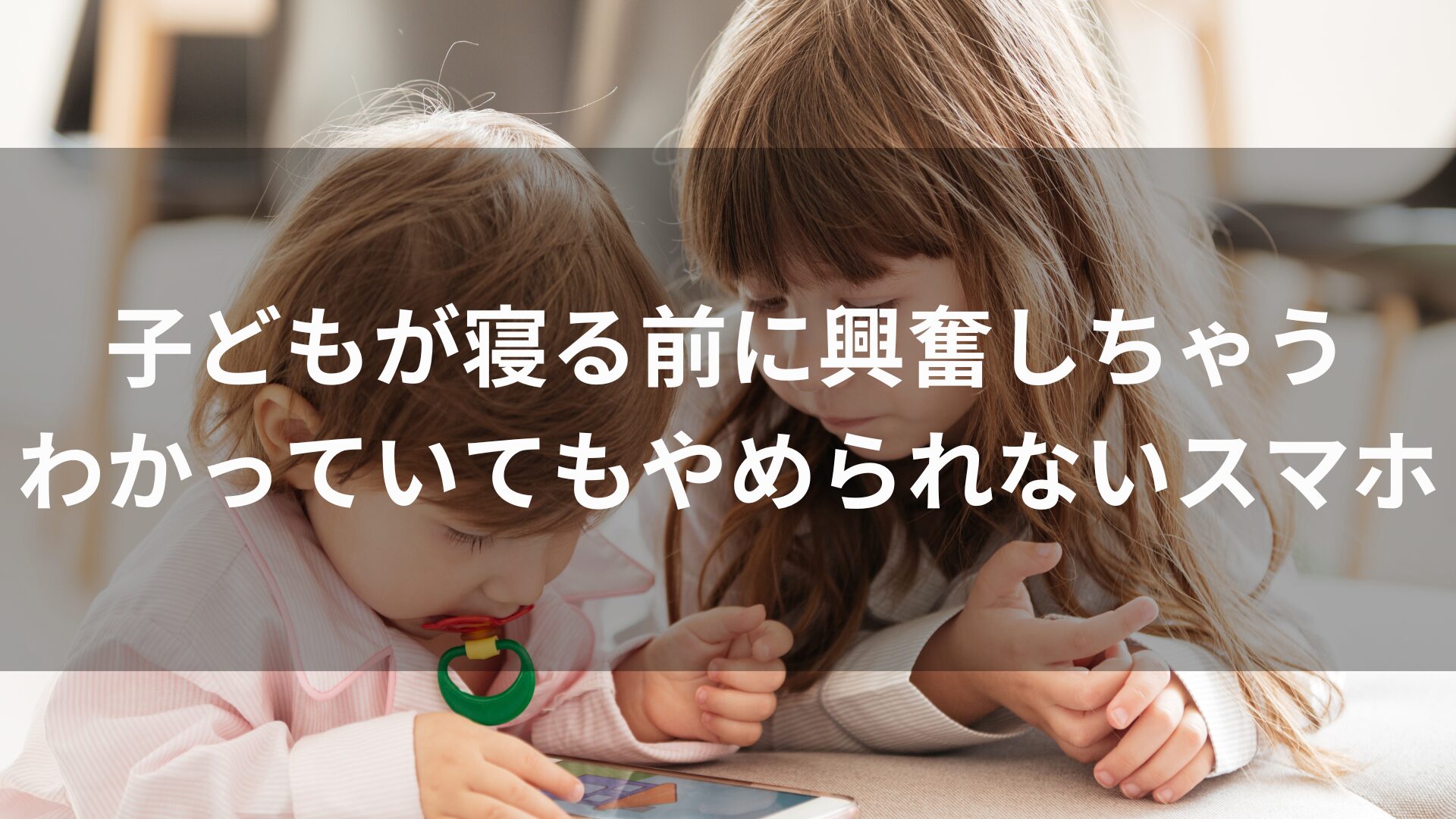

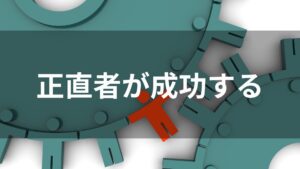


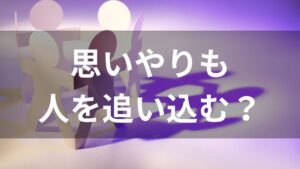
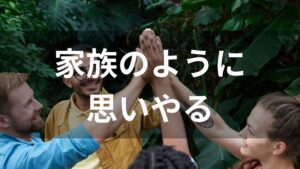


コメント